煩悩にまなこさえられて 摂取の光明みざれども
大悲ものうきことなくして つねにわが身をてらすなり |
| 高僧和讃 |
お寺に参られる年配のお方々の「・・・時間の過ぎるのが歳をとるごと、早くなっていくようだ・・・」というお声を聞きながら笑っていた自分でしたが、最近そのことを実感するようになりました。それこそ笑い話ではありませんが、四十才を越えた頃より同級生と会う機会があれば、開口一番、健康の話題が出るようになりました(実は半年ほど前からコレステロールの薬飲んでます)。すなわちこの身を通して、少しずつ死というものを意識しだしたということかもしれません。旧正月の文字を暦に見ながら、一休禅師の
「門松は冥土の旅への一里塚 馬かごもなく泊まりやもなし めでたくもあり めでたくもなし」
という一句をあらためて噛みしめています。
さて、このような前置きを書いたのには理由があります。2006年から2007年へと年が移り変わる前後、人の存在、いのちの存在というものをあらためて考えさせられるいくつかのお別れ(葬儀)をつとめさせて頂いたからです。
参列者が、生花が、ホールからあふれんばかりのお葬式がありました。
参列者が極端に少ないお葬式、中にはお葬式と呼べるかわかりませんが、ご遺体と私の二人だけでつとめたものもありました。
死者(人間)は、それぞれその背中にいろいろなものを背負っています。ですから、参列者の人数等で事の善し悪しなど問えるものではありません。
ただそこから、だれでも当たり前のごとくわかっているはずの大切な事、それをあらためて教えられるのです。考えさせられるのです。
・人はいつか必ず死にます
私たちは、いつかお別れをせねばなりません。誰一人として例外などないのです。どれほど元気であろうといつか老いて死んでいくのです。しかし、私だけはその厳然とした舞台の上に存在せず観客席の側にいるのです。そのことに気づかず、自らの欲望を満たすためにあくせくと毎日を過ごしている。その姿こそ「生死の苦海」と親鸞さまは教えてくださいます。あるご遺族の「○○が亡くなる直前に漏らした、・・・なぜ自分が、なぜ今なのか・・・というつぶやきが忘れられません」という、ため息と共に絞り出されたことばが心に突き刺さります。
・人は生まれ、そして死ぬまで(骨になるまで)だれかのお世話にならねばど うにもならぬものなのです
参列者がわずか数名のお葬式でした。その故人とは生前、若干の面識がありました。ある時その方の口からこぼれたことばが耳の奥に残っています。
「・・・私は親兄弟等と一切の縁を切りました。はるか遠くの故郷も捨てました・・・」どのような事情があったのかわかりません。ただそのことばを裏付けるように、こちらでの生き方も周囲になじまず、ある種孤独を貫いたようなものでした。その死も誰にも看取られることがありませんでした。ただ、読経しながら私は、やるせなき気持ちやそれとは逆の人情の深さ暖かさをうれしく思う気持ちと、さまざまなものが交錯していました。火葬場に向かう霊柩車のクラクションがその思いを声にしてくれたようでした。
数人のお葬式の参列者とは、故人が縁を切り、捨てたはずのはるか故郷からきてくれた実の兄弟だったのです・・・。
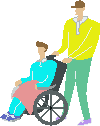 私たちは、少なくとも自分のことぐらい自分でわかっていると思っています。ただ、どうでしょうか、当たり前のごとくわかっていることのいかばかりが実生活の中で実現されているでしょうか。その私の真の姿に気づかせてくれる縁が沢山あるのです。そこにこそ還相回向の如来のおはたらきがあり、そこにこそ親鸞さまの「・・・摂取不捨の真言、超世希有の正法、聞思して遅慮する事なかれ。・・・」(ご本典総序)のおことばがあり、そこにこそ煩悩具足の凡夫との自覚が生まれるのです。繰り返し繰り返しさまざまな縁の中に仏法を聞いていきましょう。悲しみの、苦しみの、痛みのそして喜びのお念仏の中に新たな出遇いがあります。阿弥陀さまに背を向けて生きている私、しかし自らの影に目が向いたとき、すでに智慧の光に照らされていた事に気がつくのです。 私たちは、少なくとも自分のことぐらい自分でわかっていると思っています。ただ、どうでしょうか、当たり前のごとくわかっていることのいかばかりが実生活の中で実現されているでしょうか。その私の真の姿に気づかせてくれる縁が沢山あるのです。そこにこそ還相回向の如来のおはたらきがあり、そこにこそ親鸞さまの「・・・摂取不捨の真言、超世希有の正法、聞思して遅慮する事なかれ。・・・」(ご本典総序)のおことばがあり、そこにこそ煩悩具足の凡夫との自覚が生まれるのです。繰り返し繰り返しさまざまな縁の中に仏法を聞いていきましょう。悲しみの、苦しみの、痛みのそして喜びのお念仏の中に新たな出遇いがあります。阿弥陀さまに背を向けて生きている私、しかし自らの影に目が向いたとき、すでに智慧の光に照らされていた事に気がつくのです。
私たちに出来ることは親鸞さまがいのちをかけ、人生をかけ、お示し下さった真教(お念仏の教え)の確かさを普段の生活の中に、自らの頭で、自らの身を通し証していくことです。それこそが浄土真宗の門信徒のまごうことなき仏道です。 |
|
※還相回向 |
浄土に往生したものが、菩薩の相(私たちが仏法にふれていく機 縁となるはたらき)をとり再び現世に還りきて、衆生を救済する はたらきを阿弥陀如来から与えられること |
|
| 前回の「住職から」へ |

