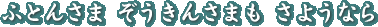
ある死刑囚が処刑される前に詠んだうたです。わが死が近づくことを感じて、今までに踏みつけにしていたふとんが、今日の今日までこの自分を休ませてくれた。この汚いぞうきんが、この狭い部屋をきれいに拭き取ってくれた、と感じ取れた。そのとき「ふとんさま」「ぞうきんさま」と「さま」をつけて拝める身になったのです。すなわち自分を見つめ自分の
いのち の在りように目が開かれていったのです。
一昨日からいよいよ「裁判員制度」が始まりました。確率的にはどうかわかりませんが、自分が裁判員になる可能性もあります。その時、もし死刑の求刑も考えられる事件であったとしたら・・・。果たしてどのように判断していくのだろう。事件の凶悪性、被害者の数、そしてまた被告の更生の可能性等々、人を裁くことの難しさを痛感します。皆さまどうでしょうか。何が正義なのか、何が常識なのか、罪の重さに対する世論の認識もその時代によって大きく変わります。この制度を運用するに当たり、量刑(死刑の存排を含めた)等の周辺整備やもう一段の議論が必要であるように感じます。ただ何より自分自身が遺憾に思うのは、重要な社会制度が開始されるとき、人ごととして、あまり気にも留めていなかった。そしてそれ故、ほとんどその中身、問題点など知らなかったという事実です。
お念仏の教えに生きることは、常に社会に目を向け、その中でいろいろな角度から、いのち を考えていく営みです。わたしたちの生き方・考え方を揺さぶる事象が激流のように押し寄せる今日、念仏者として押し流されぬ眼と耳をお互い養っていきたいものです。
|

