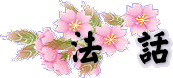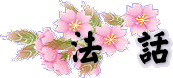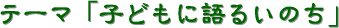 |
鹿児島国際大学短期大学部助教授 種村エイ子先生
西本願寺鹿児島別院「ハートフル大学」6月21日講演より |
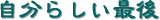 |
私の場合は、退院した後で二週間に一度坑ガン剤をもらうために病院の外来に通ってたんですけど、その時に「実はあなたのご生存率は二十パーセントです」って言われたんです。その時はものすごく辛かったですね。
なぜかというと、周りに誰も仲間がいない、どうしょうもない孤独感。周りに患者はたくさんいるけれど、どうしても孤独なんですね。周りの人とは心が通じ合ってない。看護師さんだっているのに、外来の看護師さんっていうのは患者さん一人ひとりと向き合うような時間は全くありません。次から次に患者さんを呼び入れないといけないですから、「あの人落ち込んでるな」「あの人辛そうだな」「なんか声かけてあげたいな」と思っても、そういうことは許されないのです。それで病院の中にそういうことを受け止めてくれる人が全然いない、ということをその時にイヤというほど感じました。
私はそういう絶望感を味わった後、情報をもとめて、いろんな所をさまよい歩きました。その結果いろんな出会いがありました。私の場合は図書館の仕事をしていましたので、鹿児島市立図書館にせっせと通いました。でも自分がガンだっていうことを周りに知られるのは嫌だと思ってたので、ガンの本を借りることがなかなかできなかったんですね。
でもパラパラっとのぞいた本の中でずいぶんいろんな情報を得ました。
なかでも、たまたま手に取った雑誌に、鹿児島中央駅の近くで堂園メディカルハウスというちょっと変わった診療所をやってらっしゃる、堂園晴彦先生が書かれたエッセイに出会ったんです。
まだ当時はそのような診療所を作ってらっしゃらなくて、まるでなんか普通のお家みたいな、ほんとにこれが病院だろうかっていう感じの所だったんです。火鉢が置いてあって、火鉢を囲んで患者さん同士がおしゃべりしたりするような所でした。
そういう場所で患者仲間に出会って、そのことで私はもう一度「ああ、そうか。生と死っていうのは裏表なんだ」という、それはつまり私がずっと避けてきた死を考えるということが、実は自分の今生きていることを考えるっていうことなのだっていうことに気がついたんですね。
堂園晴彦先生は「人間は生きたように死んでいく」というのをいつも言ってらっしゃるんです。その時は何となくそういう言葉に反発を感じていたんです。ですが、そのホスピスで自分らしい最後を貫いていかれた方々に出会うこあdとによって、やっぱり自分自身のいのち、自分自身の人生というのは自分で責任を持って、自分で豊にしていかなきゃいけないんだってだんだん思うようになったんですね。 |
 |
 |
そしてもう一つ。市立図書館で出会った「生の授業 死の授業」という本があります。
これは金沢市の小学校の金森俊郎という先生がお書きになりました。この先生は普通だったら校長先生になってもおかしくない年齢の先生ですが、ずっと定年退職まで一教師でいたい。ずっと子どもたちと最後まで向き合っていたい。
というのでとってもユニークな教育実践をされている方です。
一昨年でしたか、NHKスペシャルで金森先生の教室を一年かけて取材した番組が放映されたんです。それを見たうちの学生たち、小学教師を目指している学生この先生の授業をビデオで見て、金森先生をうちの学校にぜひ呼びたい。あんな先生になりたいって言うので、何十通もの手紙を書いたおです。とてもご多忙な先生なんですけれど、うちの学生たちの熱意に動かされて、今年の二月にうちの大学に来て講演をしてくださいました。
私が最初にこの「生の授業 死の授業」という本に出会ったのは、今から十年ほど前になります。生の授業っていうのは、この表紙写真じゃちょっとわかりにくいかもしれませんけど、小学生たちが白い産着の赤ちゃんをだっこしてる写真があります。この金森先生の学級では、お腹の大きなお母さんを学級に招いて、お腹を触らせてもらって、「おばちゃん、元気な赤ちゃん産んでね」とか、そういうふうに励まして、それで生まれた後にまた赤ちゃんを学級に連れてきてもらって、みんなで代わる代わるだっこさせてもらう、そういう授業をしたのです。
そして、そのクラスが次の年、また金森先生に受け持ってもらいます。
今度は末期ガンの患者で当時五十歳の泉沢美枝子さんという、乳ガンが体中に転移して自分自身ももういのちが長くないってことを自覚されている方に来ていただいて、いわゆる死を語る授業というのをされたんだそうです。その授業がされた当時は今から十数年前ですから、おそらく日本では始めての授業だったんではないかなと思うのです。
今では、堂園先生も患者さんを小学校の教室に連れて行っていのちの授業をやっておられます。
私はそれに出会って、私ではもう生の授業はできないけれど、死の授業だったらできるかもしれないというふうに思ったんです。それで金森先生に手紙を書いたんです。泉沢さんはその後亡くなってしまったんですけど、本のなかでしかお会いしたことのない泉沢さんの遺志を継いでそういう授業をやりたいなと思って授業を始めたのです。
今の子どもたちは自分自身の存在に自信を持つということができないのではないかと思います。中学校や高校などに行くと、「自分は一度死のうと思った」と言う子どもたちが結構いるんですね。そこで、私の授業ではまず、そういう子どもたちに対して、自分たちのいのちっていうのはどんなにかけがえのない存在なのかってことを伝えるようにしています。
現在は、それがまず大事なのではないかって思うのです。 |
 |
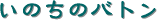 |
その私の授業で使った教材で、「驚異の小宇宙 人体生命誕生」という本があるんです。これもNHKスペシャルでずっと以前に放送した番組なのですが、その中に、私たちのいのちっていうのは、お父さんの持っていた三億個の精子とたった一個の卵子が出会って生まれてきたのだということが、とてもわかりやすく書いてあります。
例えば子宮から卵管までたどり着ける精子は、約三億個の中の約六万個なのだそうです。さらに卵子の所までたどり着けるのはせいぜい百個ほどの精子が一個の卵子の中に入り込もうとして一生懸命がんばるんですけど、結局一個だけしか入り込むことができない。残りの精子は受精することができないんです。
そうやって受精した受精卵は、また卵管をずっと戻ってきて子宮の中に着床します。
いわゆる十月十日ですね。大事に大事に育てられて生まれてくるんです。
そこでちょっと興味深いのが、受精後三十二日目からのたった一週間で、生命の記憶をたどると言われているのです。つまり、魚みたいにヒレや尻尾がある時期を経て、そして約二百八十日の間に二千倍の大きさになると言われています。
この本のなかでは赤ちゃんが東京ドームの中で寝ている写真があります。
なぜかというと、受精卵っていうのは顕微鏡で見ないと見えないぐらい小さい物なんです。それを二千倍にして約三千グラム、約五十センチの新生児になって生まれてくるんですけれども、二千倍っていうのがなかなか実感できないと言うので、受精卵の大きさを野球ボールの大きさに例えたら、野球ボールを二千個並べたら東京ドームの屋根ぐらいの大きさになるんだというのが書いてあるのです。
それで子どもたちは、「ああそうか、 野球ボールが東京ドームの屋根ぐらいの大きさになって自分は生まれてきたんだ。だからお母さんってすごいんだな」っていうふうに思うんです。女の子たちには、そういうふうにしてあなたたちは将来赤ちゃんを育てなきゃいけないんだから、今ダイエットなんかしてる場合じゃないんだよっていうふうに言ってるんです。その一つひとつのいのちは直接お父さんお母さんからもらったんですね。
相田みつをさんが「いのちのバトン」という詩にされています。
父と母で二人、直接命をもらったのはお父さんお母さん二人からいのちをもらったんです。
でもそのお父さんとお母さんは、そのまた両親からいのちをもらったので、自分にいのちをくれた人は父と母とその両親の四人。そのまた両親で八人。こうして数えてゆくと十代前まで私たちのご先祖さまをさかのぼると、十代前では千二十四人になるそうです。二十代前までさかのぼると、いったいどれぐらいになると思いますか。
小学生に聞くと、二千四十八人というふうに答えてくれるんですけど、実はなんと百万人を
越すんです。
「過去無量の いのちのバトンを 受け継いで いま ここに 自分の番をいきている
それが 貴方の ″いのち″です それが 私の ″いのち″ です」
というように相田みつをさんは詠っています。
「こんなにたくさんの、本当に数えきれないぐらいのたくさんの人がいのちのバトンを運んでくれたから、皆さんにいのちのバトンが渡ってきたんだよ」と伝えているんです。 |