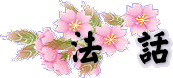 |
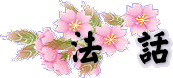 |
「・・お話ししたことは、あと僅かしか時間がない人間のいう”本当“のことですから、いろんな所で伝えて下さいね・・」 このことばは、今年のお盆にご往生された、ある女性の下さった最後のことばです。季節は移ろいましたが、まぶたを閉じると病室から見えた夏の情景が鮮やかに甦ります。お寺のご門徒さんで、以前お元気な頃は、教区や組の行事によく参加して下さいました。また長女さんが私と同級生だったこともあり私個人にとっても馴染みの深い方でした。幾度かの入退院を繰り返されましたが、六月の末にホスピス病棟のある病院に転院されたと聞いたとき、どうにかもう一度お会いしたいと思いました。  ご往生の数週間前です。会える状態であるかどうか、危惧しながら病室に行きますと、意外な笑顔で迎えて下さいました。「ベッドに横になったままでゴメンなさいねー」とおっしゃりながら、転院されてからの様子を穏やかにお話しされます。そして、思い出話などひとしきり花が咲いた後、急にしみじみとしたお顔で「今、毎日がとっても愛おしい、僅か一時間がとっても大切なの」さらに「今、私は幸せですよ」と。「この時になって、当たり前のことを実感してます・・。私を支えてくれていたのはいやいるのは、まわりの人たちの沢山の暖かい思いでした。その中でいま生かされそして逝くことができます・・。昔、あなたのお母さんと一緒にお聞きした仏さまのお話が懐かしく、そして有り難く胸に迫ります。ふいにお念仏がこみ上げてきます・・」。夕食の時間が間近になってきました。「またお会いしましょう」という言葉をいえないでいる私に向かい「お葬式はお願いね」と満面の笑みでおっしゃった後に、冒頭のことばがお別れのあいさつでした。帰路、ハンドルを握りながら目に映るいつもと変わらぬ暮れ方の風景が、何ともやるせなく、しかし輝いていました。たった今聞いたばかりのことばを反すうしながら、その時ふと肩の力が抜けたような気がしました。自分の身を通し聞かせていただいたことを素直に話していけばいいのだと。 ご往生の数週間前です。会える状態であるかどうか、危惧しながら病室に行きますと、意外な笑顔で迎えて下さいました。「ベッドに横になったままでゴメンなさいねー」とおっしゃりながら、転院されてからの様子を穏やかにお話しされます。そして、思い出話などひとしきり花が咲いた後、急にしみじみとしたお顔で「今、毎日がとっても愛おしい、僅か一時間がとっても大切なの」さらに「今、私は幸せですよ」と。「この時になって、当たり前のことを実感してます・・。私を支えてくれていたのはいやいるのは、まわりの人たちの沢山の暖かい思いでした。その中でいま生かされそして逝くことができます・・。昔、あなたのお母さんと一緒にお聞きした仏さまのお話が懐かしく、そして有り難く胸に迫ります。ふいにお念仏がこみ上げてきます・・」。夕食の時間が間近になってきました。「またお会いしましょう」という言葉をいえないでいる私に向かい「お葬式はお願いね」と満面の笑みでおっしゃった後に、冒頭のことばがお別れのあいさつでした。帰路、ハンドルを握りながら目に映るいつもと変わらぬ暮れ方の風景が、何ともやるせなく、しかし輝いていました。たった今聞いたばかりのことばを反すうしながら、その時ふと肩の力が抜けたような気がしました。自分の身を通し聞かせていただいたことを素直に話していけばいいのだと。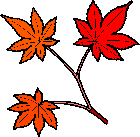 二年前から、隣寺と協力してお寺の「子ども会」を始めました。しかし今の子供たちはなかなかの多忙、参加してくれるのは、低学年以下が一番多いという現状です。そこでいつも迷っていました。おつとめの後の『お話し』をどうすればいいのかと。これまでお寺の門をくぐったことがない、まして小さい子供たちの前で、どのように話せば聞いてもらえるのか。いろいろな少年教化の法話集を参考にしながらも、こんな話をしてわかるだろうかという思いでその時間を消化していました。「汝 自らまさに知るべし」無量寿経のおことばです。このおことばがふいに浮かんで来ました。私自身、何を仏さまからいただいているのか、何に気づかされているのか、そしてどんな思いを伝えたいのか。話の技巧ばかりに目を向けてる自分がいました。当たり前のことですが、仏法に照らされ心動かされたことを自身のことばで話していくということの意味をあらためてかみしめた一瞬の出遇いでした。 二年前から、隣寺と協力してお寺の「子ども会」を始めました。しかし今の子供たちはなかなかの多忙、参加してくれるのは、低学年以下が一番多いという現状です。そこでいつも迷っていました。おつとめの後の『お話し』をどうすればいいのかと。これまでお寺の門をくぐったことがない、まして小さい子供たちの前で、どのように話せば聞いてもらえるのか。いろいろな少年教化の法話集を参考にしながらも、こんな話をしてわかるだろうかという思いでその時間を消化していました。「汝 自らまさに知るべし」無量寿経のおことばです。このおことばがふいに浮かんで来ました。私自身、何を仏さまからいただいているのか、何に気づかされているのか、そしてどんな思いを伝えたいのか。話の技巧ばかりに目を向けてる自分がいました。当たり前のことですが、仏法に照らされ心動かされたことを自身のことばで話していくということの意味をあらためてかみしめた一瞬の出遇いでした。『念仏の声を子や孫に』 今一度原点に戻り、たった一人でもいい、私の子や孫に、あるいは身近な子供たちに、繰り返しでもいい、身を通し味わった仏法の喜びを自分の言葉で伝えていく努力をしましょう。「最近何かに感動しましたか?」どこかで聞いたようなセリフですが、とても大切なことだと思います。そのためには、常々、仏法のアンテナを磨くことに努めたいものです。
|