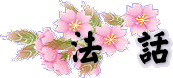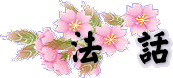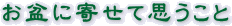 |
| 性原寺住職:安満浩二 |
無縁社会
「無縁社会」「無縁死」という言葉を最近よく耳にします。あるいは私自身が敏感になっているのかもしれません。これは、本年1月末に放送されたNHK特集「無縁社会〜“無縁死”3万2千人の衝撃〜」が、大きな要因だと思います。驚いたことに1番大きな反応を示したのは、諸条件はありますが、30代,40代という年齢層であったという事実です。みなさまの中にもご覧になった方が、少なからずおられるのではないでしょうか。番組のホームページ上に、制作者のコメントとして『・・・なぜ誰にも知られず、引き取り手もないまま亡くなっていく人が増えているのか。・・・かつて日本社会を紡いできた、地縁・血縁といった地域や家族・親族との絆を失っていったのに加え、終身雇用が壊れ、会社との絆であった社縁までが失われたことによって生み出されていた。・・・日本人がある意味選択し、そして構造改革の結果生み出されてしまった無縁社会。番組では「新たな死」が増えている事態を直視し、何よりも大切な「いのち」が軽んじられている私たちの国、社会のありかたを問い直す』という一文が掲げてあります。
最近、お参りに行った先で「・・・に迷惑をかけたくない」あるいは「自己責任」という言葉をよく耳にします。また、過去帳の整理、お墓などの相談をお受けする時にも「後の者に負担がかからないように・・・」という意味合いの言葉がしばしば使われます。失ってはならない大切な“こころ”が、何か大きなものに飲み込まれていくような焦燥を感じるのは私だけでしょうか。 |
お盆とは
今号は、特にお盆の季節ということで、お盆が今の社会に問うている意味を考えてみたいと思います。お盆の起源で私たちに一番身近なのが「仏説盂蘭盆経」のお話です。かいつまんで言えば、お釈迦様の十大弟子の一人である目連尊者が、修行の過程で身につけた神通力により、今は亡き母親の姿を餓鬼道に見つけます。そして苦しき餓鬼道から、母親を救う手だてをお釈迦様に尋ねます。お釈迦様の教示に従い安居の明ける日(お盆)に多くの僧侶を招き、供物を捧げ供養すると母親は無事に救われていったという内容です。この経が私たちに突きつけるのは何かというと、我が子(目連尊者)を育てるため餓鬼道に落ちる因を作ってしまう母親の姿であり、そしてそれは、私たち一人一人がこの世を生きる姿でもあるということです。すなわち「私たちの“いのち”は、多くのご恩に支えられた存在である」とともに「私たちは、お互い迷惑をかけることなしには生きることができない」という人生の実相です。 |
“仏の絆”の再構築
ここから導かれるのは、私たちが今、共に生きる社会を“仏の教え”という視点から見直し、それを基に新たな絆(縁)を築いていく努力を重ねよということではないでしょうか。少なくとも「助けて」という声を上げられる、そしてその声を受信できる社会を取り戻せるように。「御同朋の社会」を目指すとはこのことに他ないのではないでしょうか。
ただ、性急に具体的な社会活動を行えといっているのではありません。私たちに求められるのは難しいことではなく、今出来ることです。お盆を始め法事、あるいはお寺の行事等で、子どもから大人まで有縁の方々が集まるような時、「仏の教えを語る場」、「仏の教えを通して社会を見つめる場」をあなたにまず作って頂きたいのです。
今年のお盆、仏事の原点に返り、みなさま楽しく、そして有意義に過ごして下さい。 |