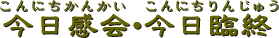 |
| (中央仏教学院講師 鎌田宗雲師 「ないおん」掲載より) |
私は、俳優の緒方拳さんが大好きです。彼が数年前に『恋慕渇仰』という本を発行しました。
その中に「今日感会、今日臨終」という中国の古い言葉を初めて知ったときに、
「厳しい、殴られるような感じの言葉だ」と感激したと綴っています。
「言葉から殴られるような感じを受けた」と言う、緒方拳という俳優の感性の豊かさを感じます。 飽食という言葉がありますが、なにもかも鈍感になっているような現代に、殴られるような感じの言葉に出会ったという、俳優の豊かな感性にほとほと感動しました。
生きることのすべてが、もう二度とない、生涯におけるただ一度だけの出会いだから、この出会いを大切にしたいという意味の言葉でしょうか。
この本の副題が「一期一会」です。
一期一会は、千利休の弟子の山上宗二の『茶湯者覚悟十体』の言葉といわれます。
一生に一度しか会う機会がない不思議な縁が一期一会です。人生のどのような出会いも、大切な出会いであるといつも受けとめていたいものです。 |
|
|
と、詩人・八木重吉が詩っています。
八木のこの問いに、どれだけの人が答えを出すことができるでしょうか。
この詩から蓮如さまの「白骨の章」の一節を思い出します。
「さてしもあるべきことならねばとて、野外におくりて夜半のけぶりとなしはてぬれば、ただ白骨のみそのこれり。あわれというもなかなかおろかなり」のところが心に響いてくるのです。 人は得難い命を恵まれて、その一生をどのように過ごしているでしょうか。
鎌倉時代の吉田兼好が『徒然草』の三十八段に、「名利につかわれて、閑かなる暇なく、一生を苦しむるこそ、愚かなれ」と、愚かしい生きざまを批判しています。
『徒然草』が世にでてから何百年が過ぎたでしょうか。
時代や環境が変化しても、人の生きざまはあまり変わっていないように思いますが、どうでしょうか。 私に厳しい声が聞こえてきます。
「今一度、得難い命を恵まれて、生きていることを、今一度見直すべきでないか」と、蓮如さまが私に問いかけているように思えます。
四月は、お釈迦さまが生まれた花祭りの月です。お釈迦さまが伝えてくださった尊い
教えは、今の私に何を伝えてくださっているのでしょうか。
この月は、とりわけ考えてみたいと思うのです。 緒方拳さんが感激した今日感会を自らの喜びとして、今が今生の別れと、どこまでも今の出会いを大切にしたいものです。
そのことに気付かせてくれるのは、み仏の教えしかありません。 |
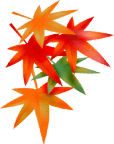 それに対して、仏教で用いられる悲願という言葉は、元来「仏・菩薩が衆生の苦しみを救うために誓われた願のことで、特に阿弥陀仏の本願をさす言葉」といわれて、どこまでも私たち人間の苦しみを、自分の苦しみとして同悲・同苦する仏の自他平等の心を表しています。それは仏に所属する言葉です。
それに対して、仏教で用いられる悲願という言葉は、元来「仏・菩薩が衆生の苦しみを救うために誓われた願のことで、特に阿弥陀仏の本願をさす言葉」といわれて、どこまでも私たち人間の苦しみを、自分の苦しみとして同悲・同苦する仏の自他平等の心を表しています。それは仏に所属する言葉です。